ふるさと納税というと、「返礼品がお得にもらえる制度」というイメージがあるかもしれません。しかし、本当に「節約」になるかどうかは、返礼品の選び方次第です。
今回のテーマは、「節約」
お得(高還元率)=節約とは限らないのです。 ふるさと納税を節約目的で活用するためには、返礼品の「お得さ」よりも「家計に与える節約インパクト」を重視することがポイントです。目的が大事ですね。
高還元率追求の落とし穴:「お得」が必ずしも「節約」ではない
多くの人が目を奪われる「高還元率」返礼品。確かに市場価格に比べて価値が高いものが手に入るのは魅力ですよね。
しかし、いくら高還元率でも、普段使っていない物をもらっても、支出は減らないですよね。
高還元率返礼品はお得ですが、節約になる、とは限らないのです。
お得に返礼品を貰えたのだから良いのではないか?と思われるかもしれませんが、それならば、最初から「豊かな浪費」として割り切り、満足度を優先して返礼品を選んだほうが納得感があると思いませんか。
節約に繋がる3つの考え方
ふるさと納税を「節約ツール」として活用するための考え方を整理しました。
①必要性の高いものを選ぶ(今の支出を減らす)
②【重要】支出行動を変える返礼品を選ぶ(習慣で節約)
③将来の支出に備える。(予防的節約)
① 必要性の高いものを選ぶ(今の支出を減らす)
普段から使っているもの、もともと購入予定だったものを返礼品でもらうことで、出費をそのまま置き換えることができます。
このとき、還元率にこだわりすぎず、「自分にとって必要かどうか」「品質が自分に合っているか」を考える事が大切です。
還元率が高くても、自分が普段使っている製品よりも高価なものを選んだところ、量が少なかった少なかった、ということもあるので、自分にとって必要十分な品質を見極めましょう。
例:
米、トイレットペーパー、ティッシュ、洗剤などの日用品
調味料、保存食品、冷凍食材などのストック品
還元率が多少低くても、「買わなくて済む」という効果は強力な節約になります。もちろん同じ品質の返礼品が複数あるなら、その中で還元率が高いものを探すのは有効です。あくまで還元率が第一ではない、という主張です。
② 【重要】支出行動を変える返礼品を選ぶ(習慣で節約)
返礼品をきっかけに、支出のパターンが変われば、その効果は一時的な寄付金額以上になります。
例:
水筒をもらって、自販機の利用を減らす
弁当箱をもらって、外食をやめて自炊弁当に切り替える
常温保存のレトルト食品をもらって、昼食のコンビニ利用を減らす
自転車をもらって通勤に活用する
こうした返礼品は、習慣全体を見直すきっかけとして非常に有効であり、寄付金額以上の節約効果を生み出せる可能性を持っています。
しかも、家計管理を通じて支出行動を把握できるリベシティの私たち向けですね。
私の話で恐縮ですが、仕事が忙しくなると朝弁当を作る余裕がなくなり、職場近くのコンビニで昼食を買う事が良くありました。
ふるさと納税でレトルトのカレーや常温のおかず類を貰ったことで、コンビニ支出を抑えることができ、寄付金額に近い節約になりました。
③ 将来の支出に備える(予防的節約)
節約というと「今の支出を減らすこと」に目が行きがちですが、 将来発生する予定の支出に先回りして備える、という発想も立派な節約です。
「必要になるのは分かっている。でも今はまだ買っていない」 そんな支出をふるさと納税で前倒ししておけば、タイミングによっては家計へのインパクトを和らげることができます。
例:
子どもが小学生になる → 自転車や学習机、学習消耗品を探しておく
災害が心配 → 防災セットやポータブル電源、備蓄羊羹などを準備
夏の旅行や帰省 → スーツケースや宿泊券を返礼品で用意
「支出の山場」を前倒しすることで、後からまとまった出費に慌てずに済み、結果的に家計を守ることに繋がります。
おわりに
ふるさと納税を節約目的で活用するなら、「高還元率」という分かりやすい指標に頼るだけではなく、家計に与える節約インパクトを基準に選ぶことが、効果的な節約につながります。
ふるさと納税を、ただのお得制度ではなく「家計管理のパートナー」として活用してみてはいかがでしょうか?
参考に 私が気になっている返礼品
水筒・飲み物系
和惣菜 常温保存が可能!職場に電子レンジがあるので、これとご飯を持っていくだけでもお弁当になります。
箱のままレンチンできる。夜、疲れて夕食を作る気力がないときにも重宝してます。
甘口なので子供も結構食べてくれるのがありがたい。です。
冷蔵庫で作るのも面倒なので、水筒にティーパックを直接入れて出勤してます。
紐を外に出して、置くと捨てるのが楽です。自販機を使う頻度がちょっと減りました。


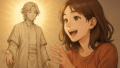
コメント